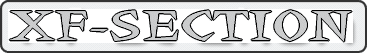
地学実験2006年度後期資料
| 地学実験の資料を添付していきます。
※ 一番下に更新情報があります。
● 月曜F類
● 火曜AB類
1. 課題
※ パソコンを使うことも練習です。データなどは自分でダウンロードしましょう。
※ レポートの提出は、1月22日(月)の昼休みに提出してください。
● 地学実験地球物理学分野第四週分課題
● 長さの計測結果のデータ
● ボールの座標のデータ(5mm 単位, 読み取りの誤差を2mm とする)
1回目
( -2, 3.5 )
( 5, 6.5 )
( 12.5, 7 )
( 19.5, 5 )
( 26, 1.5 )
2回目
( -4, -5 )
( 1, 1 )
( 7, 4.5 )
( 14, 6 )
( 21, 5 )
3回目
( 1, 2 )
( 7.5, 5 )
( 14.5, 6 )
( 22, 5.5 )
2. 各種資料
2.1 プレゼン資料
長さの計測結果について:クリック!(PDFファイル)
浮力について: クリック!(PDFファイル)
終わりに: クリック!(PDFファイル)
渦度の生成について: クリック!(PPTファイル)
2.2. 実験結果の合成写真
+ 1回め[img]http://www.meteorology.jp/XOOPS/modules/xfsection/download.php?fileid=374[/img]
+ 2回め[img]http://www.meteorology.jp/XOOPS/modules/xfsection/download.php?fileid=375[/img]
+ 3回め[img]http://www.meteorology.jp/XOOPS/modules/xfsection/download.php?fileid=376[/img]
+ 非回転[img]http://www.meteorology.jp/XOOPS/modules/xfsection/download.php?fileid=377[/img]
1. 課題
● 地学実験地球物理学分野第四週分課題
● 長さの計測結果のデータ
訂正:
画像データをパソコンで精査したところ、より正確な座標がわかりました。次のように座標を変更してください。お詫びして訂正します。
1回目 (9.5, -1), (6, 6.5), (4.5, 14)
2回目 (6.5, 17), (6, 9.5), (4.5, 2), (1, -4)
3回目 (-7, 17), (-0.5,12.5), (4,7), (6.5,0)
Q&A:
引用:
Q1. 実験テキストP.5に書かれているレポート形式に従うべきでしょうか。
A1. そうです。前回と同様です。つまり、まず、体裁は守ってくださ
い。また、今回のレポートに関しても、目的・方法などの項目は
不要で、必要に応じて方法などを書き込んでもらえれば結構です。
引用:
Q2. 読み取り誤差が2mmというのがよくわかりません。目盛の精度との兼ね合いはどうなっていますか?
A2. 目盛の間隔 5mm は、比較的正確に 5mm です。「比較的正確」の意
味は、ボールの移動距離に関して考えられる誤差のうち、読み取り
の誤差の方が、目盛自身の誤差よりも、はるかに大きいという意味
です。
まずは、ボールの移動距離を推定しましょう。
引用:
Q3. 「周期のデータTを推定せよ」とは書かれていません。誤差を考え
なくても良いのでしょうか。
A3. 理論的な曲率半径を推定するためには、当然、周期 T の推定が不
可欠だと思ったので、書く必要を感じていませんでした。周期T も
推定してください。
2. 各種資料
2.1 プレゼン資料
長さの計測結果について:クリック!(PDFファイル)
浮力について: クリック!(PDFファイル)
終わりに: クリック!(PDFファイル)
渦度の生成について: クリック!(PPTファイル)
2.2. 実験結果の合成写真
+ 1回め[img]http://www.meteorology.jp/XOOPS/modules/xfsection/download.php?fileid=368[/img]
+ 2回め[img]http://www.meteorology.jp/XOOPS/modules/xfsection/download.php?fileid=369[/img]
+ 3回め[img]http://www.meteorology.jp/XOOPS/modules/xfsection/download.php?fileid=370[/img]
+ 非回転[img]http://www.meteorology.jp/XOOPS/modules/xfsection/download.php?fileid=371[/img]
2.3. 実験時間中( 2006-01-09 午後1時過ぎ )の地震について
震源は80kmとやや深く、実験の時間の予想通り、ほぼ直下の地震でした。
詳しくは、気象庁地 震情報のページへ。

(気象庁ホームページの画像をリンク)
[img align=center]http://www.meteorology.jp/XOOPS/modules/xfsection/download.php?fileid=360,350[/img]
[img align=center]http://www.meteorology.jp/XOOPS/modules/xfsection/download.php?fileid=359,350[/img]
1. 静力学平衡のプレゼン資料
2. 実験結果
引用:※ 渡した両対数グラフは1〜100までしかプロットできません。100を越える数値(130や129)については、枠外になります。しかし、100より小さい数字の目盛り(たとえば、1.3とか、1.29)を参考にして、位置を決定することができます。そのようにしてプロットして下さい。
2.1 月曜日F類
ブロック数 発生回数
1 130
2 59
3 39
4 47
5 33
6 31
7 23
8 17
9 13
10 14
11 9
12 11
13 12
14 6
15 6
16 6
17 6
18 3
19 1
20 1
21 4
22 1
23 2
24 3
25 1
26 1
27 2
29 2
30 2
32 1
35 1
36 1
37 1
38 1
41 1
2.2 火曜日A類
ブロック数 発生回数
001 129
002 81
003 49
004 52
005 27
006 22
007 28
008 17
009 15
010 12
011 11
012 15
013 2
014 6
015 4
016 3
017 5
018 2
019 1
020 4
021 1
022 4
023 1
024 2
025 1
026 1
027 1
028 3
030 1
032 1
037 1
038 2
040 1
044 1
071 1
074 1
3. テストの解答例
1. テキスト: 地学実験テキスト第14版暫定版
2. わかりやすい記述のしかた: 記述のしかた資料
※ 参考 : ケプラーの法則(WikiPedia)
3. テストの解答例
日付: 2006/12/4
カテゴリ: 地学実験
本記事のURLは: http://www.meteorology.jp/XOOPS/modules/xfsection/article.php?articleid=151
|
|
|